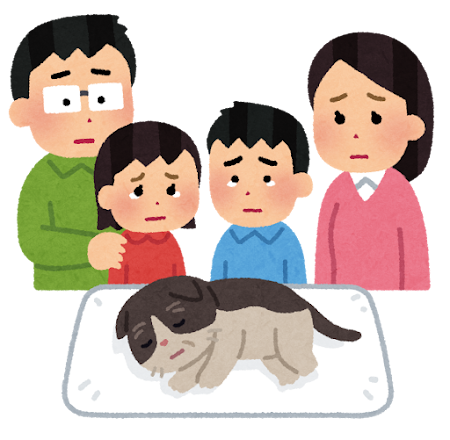こんにちは、まいたけです。
今日は犬のコミュニケーションについてお話します!!

ぼくたちのコミュニケーション方法には大きく3つあります。
1つ目は「視覚を使ったコミュニケーション」
これは飼い主さんとの生活で最も多く使っているものです。
例えば「威嚇しているとき」
まっすぐに相手を見つめ、毛をさかだてたり、頭をのばしてしっぽをたたせたり、歯をむきだします。
例えば「うれしいとき」
しっぽを横にふりながら、ジャンプしてみたり、かけまわってみたり、耳をピンとたててすましてみたり。きっとこの行動は飼い主さんにも一番伝わっている気持ちだと思います。
例えば「こわいとき」
しっぽを下げるまたは後ろ足のあいだにいれたり、耳を伏せ、上目遣いになったり、視線をずらしたり、腰をおとします。あまりにも怖い場合は、このまま威嚇行動をとることもありますし、優位な相手に対してはおなかをみせて服従姿勢をとることもあります。
例えば「遊びたいとき」
急にぼくたちがうなり声をあげてほえることがあります。そんなときはボディランゲージをみてみてください。前足をのばして頭をさげておしりをあげているときは、遊びたいんです。これを「遊びに誘うおじぎ play bow」といいます。どんなにうなっていても、これは楽しいときのうなり声。いっぱい遊んでください。
ほかにも去勢していない場合の男の子では片足をあげておしっこすることがあります。みなさんもご存知のマーキングですが、この行動も性別や優劣を表す行動だとされています。強い男の子ほどマーキングを多くするようです。
またぺろぺろとなめようとする行動も、うれしいときや怒らないでという服従行動のひとつです。
2つ目は「聴覚を使ったコミュニケーション」
ぼくたちは基本的には吠える動物です。吠えることによって、警戒をうながしたり、コミュニケーションをとろうとしています。

最近では多くのわんちゃんたちが室内飼育に移行し、吠える行動が「問題行動」として認識されるようになってきました。吠えるという行動は、本来そなわったぼくたちのコミュニケーションツールなので、こんなときは吠えなくてもいいんだよ、こういうときは吠えてもいいんだよということを飼い主さんとの生活やしつけによって学んでいくのです。
警戒してほしいときにも吠えますし、何か変なことがおきてるぞというときも吠えます。また、遊んで楽しいときにも吠えます。
うなるときは怒ってるとき。多くの方がそう思われてるかもしれません。もちろん嫌なことをされたり、怒ってるぞ!近づくな!という意味でうなっていることもあります。この場合も視覚によるコミュニケーションでいろいろな情報を発信しています。
一方で、楽しくてもうなります。遊びが楽しくて楽しくてしょうがないとき、ぼくたちはうなります。遊んでいて急怒っているのではないので、いっぱい遊んでください。
キュンキュンとなくこともあります。これは、さみしかったり、何か不満があるとき、甘えたいというとき。うれしいときのあいさつにも使うことがあります。
3つ目は「嗅覚を使ったコミュニケーション」
このコミュニケーションは飼い主さんとのやりとりの中ではあまり目立たないものかもしれません。視覚や聴覚と違ってリアルタイムの情報を伝えることはできませんが、最終的な確認をするときにやっぱり嗅覚は重要なんです。
ヒトでは指紋(フィンガープリント)が個体識別に使われていますが、動物の世界ではオドアプリント(匂いの指紋)が当たり前。それぞれみんな少しずつにおいが違うんです。
ぼくたちの嗅覚は人間以上なのはみなさんご存知だとおもいますが、ほかにも「鋤鼻器(じょびき)」という感覚器官が鼻の奥にあるんです。これはフェロモンをかぐときに大活躍。ヤギやウマなどが上唇をめくりあげて歯をだしているのをみたことありませんか?「フレーメン」とよばれるその行動はフェロモンを鋤鼻器にとりこんでいるんですよ!ぼくたち犬は、そのやりかたはできないので舌を出し入れしたり、鼻にるポンプ機能をつかってフェロモンをとりこみます。
さてコミュニケーションのお話はここまで!
また次回の更新をお待ちくださいね!!