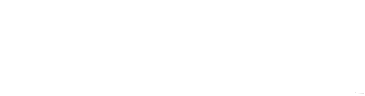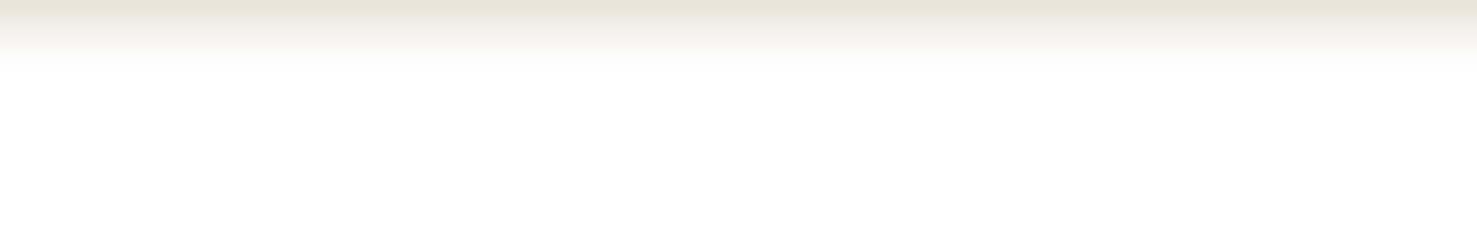ワクチン
犬
混合ワクチンは接種が推奨されているコアワクチンと、飼育環境に合わせて接種するノンコアワクチンの組み合わせによって種類が異なります。5種、6種、8種、9種、10種などがありますが、当院では5種、7種混合ワクチンを接種しています。このワクチンは、動物の命にかかわる怖い病気であったり、人にも感染しうるといった理由からペットに接種を推奨しているものです。
5種混合ワクチンと7種混合ワクチンにはどんな病気がはいっているの?
疾病 症状など 5種 7種 犬ジステンパー 鼻水、高熱、神経症状など。死亡率が高い。 ○ ○ 犬伝染性肝炎 幼犬の突然死。発熱、嘔吐、下痢、肝炎など。 ○ ○ 犬アデノウイルス2型感染症 発熱、咳、鼻水、肺炎など。混合感染により重症化。 ○ ○ 犬パルボウイルス感染症 激しい嘔吐下痢、突然の衰弱。死亡率が高い。 ○ ○ 犬パラインフルエンザ感染症 伝染性が強い。咳、鼻水、発熱など。混合感染で重症化。 ○ ○ 犬レプトスピラ感染症
(2種類)
(カニコーラ・イクテロヘモラジー)発熱、黄疸、血尿、肝臓・腎臓疾患など。千葉県でも発生しています。人にも感染します。 × ○
- レプトスピラのみのワクチンも取り扱っております。レプトスピラが入っていないワクチンを打っている場合は、レプトスピラのみのワクチンを打つこともできます。免疫獲得には時間がかかりますので、キャンプ等のおでかけの2週間前までには接種しましょう。
- 当院では世界小動物協会(WASAVA)によるワクチンに関する推奨基準を主に導入しております。2024年にこの基準が更新されたこと、千葉県ではレプトスピラが毎年発生していることを踏まえ、ワクチンアレルギーなどの特別な事情がない限り、基本的には7種の接種を推奨しております。
猫
ねこちゃんのワクチンもわんちゃんと同様、入っている種類により、3種と5種ワクチンがあります。(流通状況により5種ではなく、クラミジアを除く4種となることもあります)当院ではどちらのワクチン接種も対応可能です。しかし、2024年に世界小動物協会(WASAVA)によるワクチンに関する推奨基準が更新され、猫白血病発生地域(香取周辺地域も該当します)では室内飼育であっても4種以上のワクチンが推奨されることとなりました。そのため、当院ではお外にパトロールにいく子はもちろん、室内飼育猫ちゃんも猫白血病ウイルスを含めた5種混合ワクチンを推奨しています。
3種混合ワクチンと5種混合ワクチンはどんな病気がはいっているの?
疾病 症状など 3種 5種 猫カリシウイルス感染症(FC-7) 風邪様の症状。肺炎や口腔内に潰瘍をつくることも。 ○ ○ 猫汎白血球減少症 風邪様の症状。肺炎や口腔内に潰瘍をつくることも。 ○ ○ 猫ウイルス性鼻気管炎 発熱、下痢、食欲不振など風邪様の症状。 ○ ○ 猫白血病ウイルス感染症 発熱、貧血など。症状がでないことも。 × ○ 猫クラミジア感染症 発熱、咳、鼻水、肺炎など。混合感染により重症化。 × ○
混合ワクチンはいつから?何回打つの?
子犬・子猫は母乳からもらった移行抗体により、若ければ若いほどワクチンの効果が弱くなります。そのため当院では、移行抗体が減少してくる生後2ヶ月齢以降に1回目のワクチン接種を行います。その後、3か月齢、4ヵ月齢で接種していきワクチンプロトコルは終了となります。WASAVAによると、生後6ヵ月齢では移行抗体がほぼ消失していることから、生後6ヵ月齢~1歳未満の間にブースターの4回目ワクチンとして追加接種を推奨しております。当院におきましても、ご家族とご相談の上、ブースターを接種する機会が増えております。より確実に免疫をつけたい場合はぜひご相談ください。また1歳以降でワクチンを開始した場合、初めて暴露された抗原に対しては、1回の接種でしっかり免疫ができないことが多いため、1ヶ月の間をあけて、2回目ワクチンを接種します。その後は全頭毎年1回の接種を推奨しています。
混合ワクチンは毎年打つの?
海外ではワクチンは3年に1回の接種でよいとされてきていますが、日本で多く使用しているワクチンとは種類が異なります。さらに個人差がありますが、ワクチンを打っても1年もたたずに抗体価が下がることもあります。最もよい方法は、ワクチン接種前に抗体価を調べ、その値に応じてワクチンプロトコルをくむことです。しかし、検査自体も高額なため、なかなか難しいのが現状です。(当院でもご希望があれば、抗体価検査を行うことは可能です。)そのため、当院では毎年1回のワクチン接種を推奨しています。
ワクチン接種により予防できる感染症にかかっていると診断または疑われる子を各都道府県の半数ほどの病院が経験しているとのデータがあります。(2013~2015年、全国600件 伴侶動物ワクチン懇親会調べ)日本は欧米と比較してもワクチン接種率はいまだに低いままです。多くのペット保険も、ワクチンで予防できる疾病の場合は、保険適応外となってしまいます。予防可能な病気は、やむをえない理由をのぞき予防をしてあげましょう。
日本においてもワクチン接種回数を減らすのに十分な臨床、研究データが集まった際には、当院も対応致します。
ワクチン接種の持ち物
- リードまたはキャリー(院内は必ずリード着用またはキャリーでの待機をお願いします)
- 今までのワクチン接種証明書(他院やブリーダーで接種した場合)
- 患者様の好きなおもちゃや落ち着く毛布など ・ごほうびおやつ(ワクチンを頑張った証に)♬
混合ワクチンの流れは?
- 1事前にLINE等でご予約をお願いいたします。副作用の観察時間を確保するため、午前中の接種をお願いしております。
- 2ご来院されたら、受付にお声かけください。ご予約外の場合は、自動受付をお願いいたします。
- 3 順番に看護師がお呼びしますので、各待合室でお待ちください。
慣れない病院で緊張していますので、体を撫でてあげたり、声かけをしたり、好きなおもちゃをだして少しでもリラックスできるようにしてあげましょう。
- 4 問診、触診、視診、聴診等身体検査を行い、異常がないかをチェックします。
- 5 問題がなければ獣医師がワクチンを接種します。
以前に具合が悪くなった子は相談をしながら、アレルギーをおさえる前処置を行い(約15分待ち時間)接種します。重篤な副反応でたことがある場合や慢性消耗性疾患(末期がん等)の子は、ご相談の上ワクチン接種を見送ることがあります。
- 6 接種後10~15分は当院の待合室や駐車場、お車の中でお待ちいただきます。
この待ち時間はワクチンへの急性副反応がでないかを確認していただく時間になります。
観察中に呼吸があらくなったり、嘔吐し、ぐったりするなどの異常がでた場合は速やかに申し出てください。アレルギー反応をおさえる注射を行い、状態によっては酸素吸入や点滴を行っていきます。
- 7 特に変わりなければご帰宅いただき、引き続き安静にて観察をお願いします。
遅れてくる副反応として、午前接種の場合は午後~夕方にかけてお顔がむくんだり、蕁麻疹(特におなか)がでたりすることがありますので、その場合はご来院ください。
- 8 免疫反応が落ち着いてくるのに2週間ほどかかりますので、シャンプーや手術などのご予定がある場合は、それ以降をおすすめいたします。
混合ワクチンを打てないとき、打ったあとの注意点は?
人間のインフルエンザ予防注射のときと同じように、動物の予防注射も個人差はあるものの少なからず体に負担をかけます。そのため、事前のおうちでの様子(おうちでリラックスしているとき)が少しでもいつもと違うようであれば、ワクチン接種は控え、延期しましょう。いつもよく観察されていることと思いますが、ワクチン接種のときには元気食欲など注意して見守ってあげましょう。また接種後は、動物もなれない病院のストレスなどにより疲れていますので、ゆっくり休ませてあげてください。
- 接種前に注意しておくこと
-
- 元気食欲はいつも通りか
- 過剰に興奮していないか(遊び、運動など)
- 体は熱くないか
- おしっこやうんちに変わりはないか
- お腹がはっていたり、呼吸がはやくないか
- 咳やくしゃみがでていないか
- アレルギー体質ではないか(問診時にお申し出ください)
- 妊娠はしていないか
- 寄生虫がいる可能性はないか
- 様子をみる時間を確保するために、なるべく午前中に接種を予定する
- 接種後に注意しておくこと
-
- 様子をよくみる
- おうちで安静にする
- 激しい運動をひかえる
- シャンプーやブラッシングはひかえる
- 他の犬との接触をひかえる
- おでかけをひかえる
ワクチンの副反応
体質により副作用がでることがあります。重篤なものほど発生頻度は下がりますが、毎年の接種で大丈夫だったとしても今回の接種ででることもありますので、注意が必要です。
多くの場合は一時的で、数時間~数日でおさまります。慣れない病院での過度な緊張や疲れによっても嘔吐や下痢、元気食欲低下がみられることがあります。
- 自宅で2、3日経過観察し、改善がなければご来院ください。
-
- 嘔吐・下痢
- 発熱
- 元気食欲減退
- 注射部位の痛み、軽度の腫れ
- ワクチンアレルギー反応の可能性が高いです。ご来院ください。次回からは相談の上、前処置での接種となります。
-
- 全身の赤み、かゆみ
- 蕁麻疹(腹部で発見しやすい)
- 顔のむくみ(唇まわりで発見しやすい)
- 重篤な副作用です。多くは接種後10~15分で起き、緊急を要しますのですぐにスタッフにお知らせください。
-
- 呼吸があらくうまく呼吸できていない
- 舌の色が紫色
- ぐったりして意識がない
- 立てない
- 意識が朦朧としている
ご自宅で起こった場合は、当院にご連絡いただくか、夜間などで当院がご対応できない場合は救急外来で受診してください。
狂犬病ワクチンと混合ワクチンは同時に打てるの?
ワクチンは体に少なからず負担をかけますので、同時接種は行っていません。
狂犬病ワクチンは「不活化ワクチン」、混合ワクチンは「弱毒生ワクチン」という種類のワクチンになります。それぞれ体への影響が異なります。
次のワクチン注射まで、狂犬病ワクチンの場合は1週間、混合ワクチンの場合は3~4週間あける必要があります。そのため、狂犬病ワクチンを打ってから、1週間後に混合ワクチンを打つと短期間にワクチンプロトコルが終わることになります。
| 最初に | ||
|---|---|---|
混合ワクチン |
1ヶ月後 → |
狂犬病ワクチン |
狂犬病ワクチン |
1週間後 → |
混合ワクチン |
- ねこちゃんには狂犬病ワクチンの接種義務はありませんが、渡航先によっては必要になることがあります。